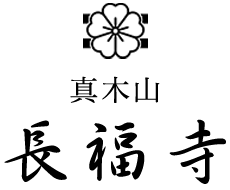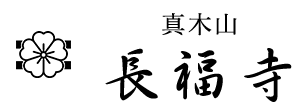長福寺の本堂
長福寺の本堂は、静寂と荘厳さを感じる心安らぐ広い空間です。
壮大な園庭では一年中を通して様々な季節の行事が開催されています。


昭和3年に建てられて以降檀信徒の仏事、法事、会議集会、また催し物にも使用され憩いの場となっています。


長福寺の境内 案内図


1:本堂
昭和3年再建。本尊十一面観世音菩薩立像を中心に、脇侍に不動明立像(室町時代)と弘法大師坐像をまつる。

2:収蔵庫
昭和62年落慶。

3:大師堂
昭和17年、真木山より地元神田青年団により移築。旧毘沙門堂、貞享年間(江戸時代初期)の建築。弘法大師空海座像、毘沙門天立像、釈迦如来座像、愛染明王坐座像(現在修復中)、地蔵菩薩立像等を安置。

4:鐘楼門
江戸時代後期、昭和5年に真木山より移築。梵鐘は戦時中に国の要請により供出された。戦後再鋳され現在に至る。

5:弁天堂
昭和35年、真木山より移築。弁才天をまつる、学問、音楽、五穀豊穣、雨乞いの神。

6:三重塔(国指定重要文化財)
岡山県下最古の文化財木造建築。総高22m、3間(5.5m)四面。
真木山より昭和24年〜26年にかけ解体移築。その際当時の山主、檀信徒の様々な逆行を乗り越えた決断と行動に深く感銘を受ける。重ねて消防団、神田村民、そして小中高生の献身的な塔部材運搬作業の奉仕あっての現在の姿である。

7:鎮守堂(旧山王宮)
室町期に建立、宝永元年(1704年)の江戸時代中期に再建。平成9年5月 本殿を真木山より移築。
その際、拝殿と幣殿は新たに再建された。本殿、幣殿、拝殿の権現造りの三間社である。寺院の守護神である山王大権現を主に祭る。
- 山王大権現 国家鎮護、寺院、檀信徒、地域を守護する
- 金比羅大権現 水の神、農耕の神(雨乞い)
- 淡嶋大明神 婦人病の治癒や子授け、安産、裁縫の神
- 稲荷大明神 五穀豊穣の神

8:虚空蔵堂
昭和36年頃、真木山より移築。2間4方(3.6m四方)、旧虚空蔵堂は8間4方(14m四方)。毎年1月第3日曜日開催の「十三まいり 虚空蔵大祭」において十三まいりの護摩祈祷が行われる。
史跡
真木山山頂の長福寺伽藍跡は長らく雑木や竹草木に覆われて荒れ果てた状態だったが、地元文化財保存会の皆様の手によって草木竹等伐採整備され現在では当時の様子を垣間見れます。
歴代院主の石塔墓地、参道、弁天池跡、鑑真の墓(およそ3m四方の石積)、鎮守堂(旧山王堂)の拝殿(既倒壊)、複数の塔頭寺院の跡地と礎石、三重塔の跡地と礎石、六地蔵ほか多くの石仏宝篋印塔等が現存している。
現地で散策し全体を見渡せば当時の真木山の大伽藍を容易に想像できる。